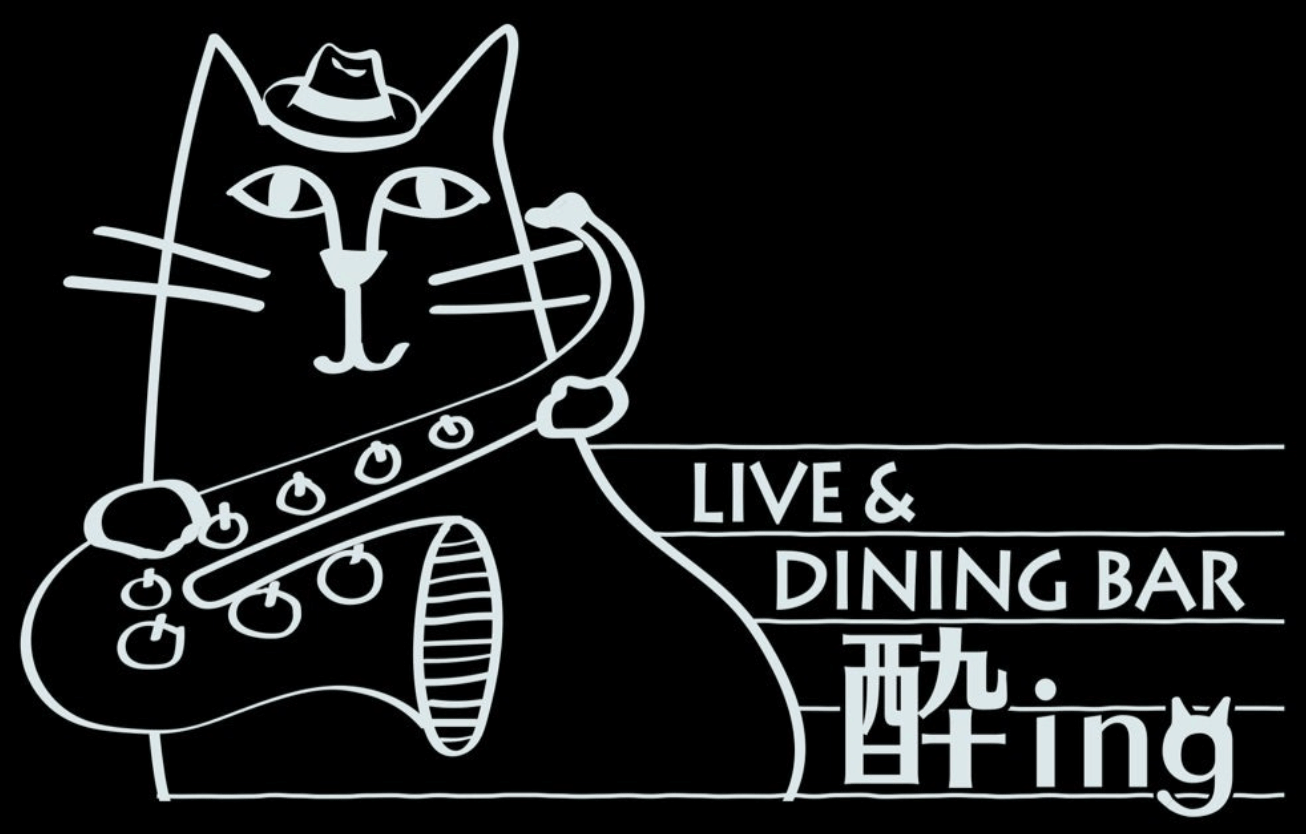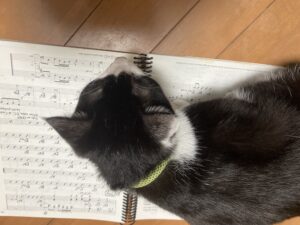以下の文章は過去に別な場所で公表したものです。趣味レベルでジャズォ学びたい人に教えてる場合という前提で書いたものです。
もう長いこと、人にジャズを教えるなんてことを商売として、本当に細々とやってきたわけです。
思い返せば、過去の自分に人を指導するような資格が果たしてあったのか?空恐ろしい気持ちになることもあります。
一方で、数多くの有名ジャズミュージシャンが、教則本、解説書、フレーズ集、教材を「我こそは」と出版したりしているわけですが、いわゆる教本コレクターを喜ばせるだけの現状ではないでしょうか?その証拠に、「私はこの本のおかげでプロになれました。」みたいな話はついぞ聞かないですよね。
なんでジャズが他の音楽より普及できていないように感じるのか?
「そりゃ難しいからだよ。」と言う人も多いとは思いますが、自分の経験も踏まえて、教える側にも問題があるのではないかと、最近思い始めました。
ということで、今回は教える側がハマってしまっている落とし穴について、考えてみました。
【多岐にわたって教えたがってしまう】
僕はサックスは楽器も含めて教えますが、他の楽器の人はジャズだけを指導します。
ある日突然気がついたのですが、ピアニストの生徒さんの方がサックスの生徒さんより上達速度が速いのです。
気がついた瞬間、理由が閃いたのですが、多分サックスの基礎練習に時間を割き過ぎていたのです。
オーバートーンとか、滑らかな運指についての練習とか、もちろん大事なことには違いないのですが、そんなことよりもっと大事なのは、ジャズの面白いところはどこかということですよ。
これを味わえる能力をまず身につけてもらうことが大事で、「ジャズって楽しい!」って思ってもらうことが大事だと思うようになりました。つまりプライオリティの問題とも言え、生徒さんの性格や経歴に合わせて、最小限度の課題から教えていくべきなのではないかと考えます。
【自分を基準に教えてしまう】
ついつい自分の成長過程を逆算し、教える側の勝手な思い込みで「こういうことができるようになるべきだ。」と考えたり、「私はひたすら◯◯◯したから、生徒さんも◯◯◯させる。」というような要求をしたり。
もちろん上手くハマる時もあると思いますが、人格も背景も環境も動機も全く人それぞれなわけですから、自分を基準にして相手のそれを押しつけるのは、その方がラクで教えた気分になるのですが、やっぱりなるべく生徒さん側を基準に何をどう教えるべきかを考える必要があると思います。
この2つの落とし穴に気をつけながら、ジャズという音楽が持つ「コミュニケーションする楽しさ」を実感するための力をまず身につけてもらうことが大事なのではないかと考えています。
そしてその力とは、演奏力も大事には違いないのですが、自分以外の楽器の役割についての理解とヒアリング能力の育成、そして何よりジャズを好きになってもらう工夫というものが、教える側に必要なのだと、個人的には確信するに至りました。